日本史というと「暗記科目」というイメージが強く、「どれだけ多くの用語を覚えられるか」に目が向きがちです。
でも、実は“暗記”に頼りすぎると、覚えては忘れ、忘れては焦り……のループに陥ってしまいます。
実際に、私自身も何度もそうした壁にぶつかりました。
しかし、ある時から「忘れるのが当たり前」と考えるようになって、勉強へのストレスがぐっと減りました。今回はその理由と、ストーリーで覚える方法について詳しくお話しします。
日本史というと「暗記科目」というイメージが強く、「どれだけ多くの用語を覚えられるか」に目が向きがちです。
でも、実は“暗記”に頼りすぎると、覚えては忘れ、忘れては焦り……のループに陥ってしまいます。
実際に、私自身も何度もそうした壁にぶつかりました。
しかし、ある時から「忘れるのが当たり前」と考えるようになって、勉強へのストレスがぐっと減りました。今回はその理由と、ストーリーで覚える方法について詳しくお話しします。

人間の脳は、もともと「忘れる」ようにできています。「エビングハウスの忘却曲線」という有名な研究でも、覚えたことの多くは1日で忘れてしまうと示されています。
ですから、「せっかく覚えたのに忘れた…」と落ち込むのは、実はまったく意味がないのです。
何度も繰り返すうちに、だんだんと“忘れづらい”記憶に変わっていきます。小テストの点が悪かったり、思い出せないことがあっても、「また覚えればいいや」と気楽に構えてください。それだけで、ずっと楽に学習を続けられます。
では、何をどう覚えていけばよいのでしょうか?
人間の脳は、「意味のない情報」はとても覚えにくいと言われています。たとえば無作為な数字の列や、バラバラな単語はすぐに忘れてしまいます。でも、そこに“意味”や“つながり”があると、不思議と覚えやすくなる。
歴史も同じです。単語の羅列を覚えるのではなく、「その出来事はなぜ起きたのか」「どうして注目されているのか」といったストーリーの中で覚えると、記憶の定着率は驚くほど上がります。
キーワードは、「〜なのに」と「〜だから」です。
たとえば「大塩平八郎の乱」は、彼が“役人だったのに”反乱を起こしたことが重要です。
普通、役所で働いている人が体制に反抗するなんて、よっぽどの理由がある。それこそが“歴史に残る出来事”なんです。
また、文化財の中には「布でできているのに現存している」ものもあります。
布は本来分解されやすいのに、今も残っている。だからこそ歴史的価値があるんです(例:天寿国繍帳)。
こうした「意外性」や「因果関係」に注目すると、日本史の出来事がぐっと生き生きと見えてきます。

最後に、私が実際にやっていた方法をひとつ紹介します。
テスト前、私はよく父に向かって、日本史や世界史の内容を時系列で語っていました。聞いてもらっていたというより、一方的に話していただけです(笑)。でもこの方法がとても効果的で、口に出すことで、自分の記憶が整理されていきました。
これは「ラーニングピラミッド」という学習理論でも裏付けられています。人は“受け身”の学習(読む・聞く)よりも、“能動的”な学習(人に教える・話す)の方が、記憶に定着しやすいのです。
保護者の方へ。もしお子さんが「ちょっと話を聞いて」と歴史の話を始めたら、ぜひ聞いてあげてください。それだけで、本人の記憶がぐっと定着します。
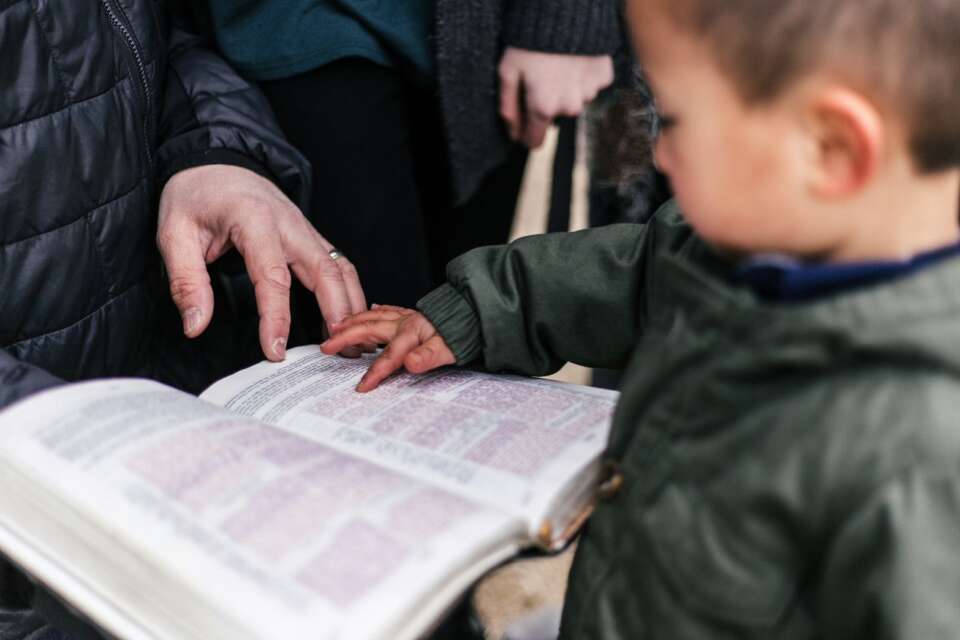
日本史は「意味」で覚えると、ぐっと楽になります。忘れるのは当たり前。だからこそ、何度も触れて、ストーリーの中で“意味”を見つけていきましょう。
歴史に残る出来事は、単なる羅列ではありません。「なぜ」「どうして」「そんなはずじゃないのに」といった“物語”の中にあります。そう思えば、日本史の勉強はきっと楽しくなります。
そして何より、あなたが感じた「面白い」「変だな」「なるほど」が、最強の記憶フックになります。
一緒に、日本史を“自分のもの”にしていきましょう。